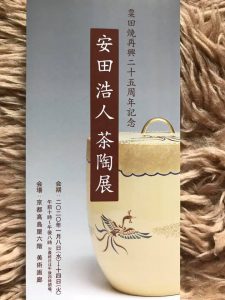春には桜色の帯を合わせている小紋の着物。秋には、薄茜色を合わせたら、どうなるか。
春には桜色の帯を合わせている小紋の着物。秋には、薄茜色を合わせたら、どうなるか。
実は、この帯に出会ったとき、さんざん迷ったんです。もうすでに桜色をお持ちじゃないですか。と言われれば、その通り。しかし、ハイビスカスで染めたと知って、呼ばれてしまったのですね。20代 から大好きな花ですから。
から大好きな花ですから。
訪れたのはノートルダムの和中庵。近江商人・藤井彦四郎の邸宅として建てられた昭和初期の名建築で、1949(昭和24)年にノートルダム教育修道女会が取得。現在は東山にある中学高等学 校の敷地内にあります。
校の敷地内にあります。
入口は洋館、奥が和風建築。人が少なかったので、いろいろな角度で撮影させてもらいました。中高等部は写さないという条件で。